社外取締役鼎談
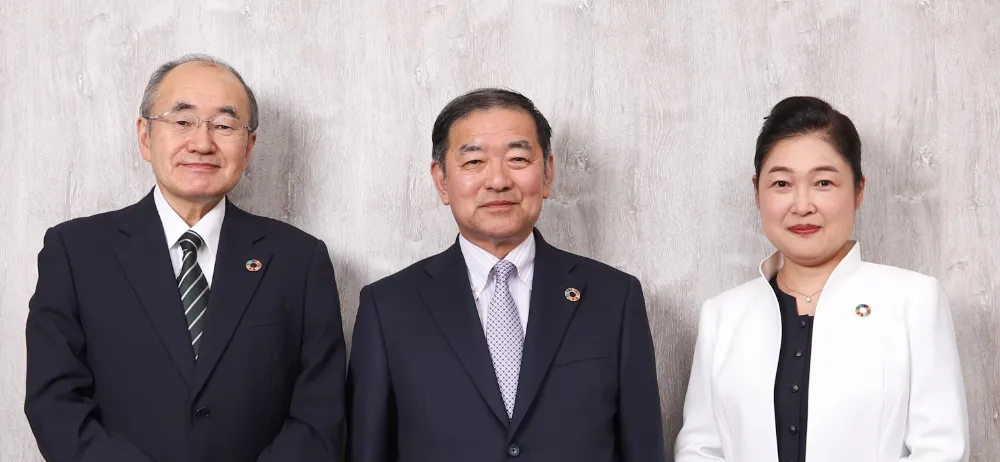
社外の視点から見たガバナンス改革の進展
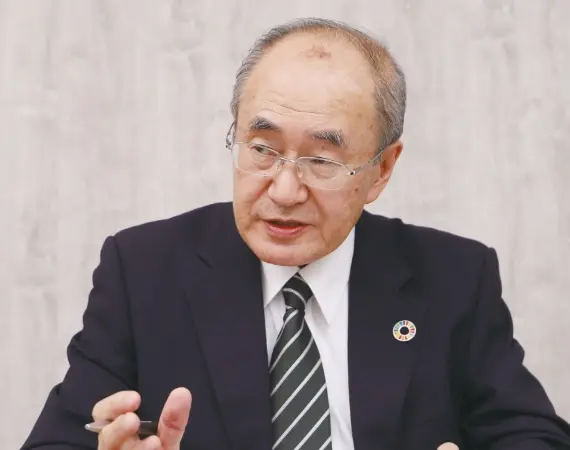
独立社外取締役 監査等委員
内藤 憲一
1982年 4月 宇部興産株式会社(現UBE株式会社)入社
2002年 5月 宇部テクノエンジ株式会社(現UBEマシナリー株式会社)管理部長
2008年 6月 同社取締役管理統括部長
2014年 6月 株式会社ティーユーエレクトロニクス 常務取締役管理本部長
2017年 6月 宇部エクシモ株式会社常勤監査役
2023年 6月 当社取締役監査等委員(現任)

独立社外取締役 監査等委員
林 肇(指名・報酬委員会委員長)
1983年 4月 三重労務管理センター入社
1986年 4月 弁護士登録 大脇・鷲見合同法律事務所入所
1989年 4月 明和綜合法律事務所入所
1996年 5月 さざんか法律事務所所長(現任)
2020年 6月 当社監査役
2021年 6月 当社取締役監査等委員(現任)
2023年 6月 当社指名・報酬委員会委員長(現任)

独立社外取締役 監査等委員
中田 朋子
1997年 4月 判事補(東京地方裁判所)任官
2000年 6月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
2002年 8月 ニューヨーク州弁護士登録
2015年 3月 The American College of Trust and Estate Counsel International Fellow(現任)
2017年 4月 The International Academy of Estate and Trust Law Academician(現任)
2020年 12月 東京ヘリテージ法律事務所所長(現任)
2021年 6月 当社取締役監査等委員(現任)
2023年 6月 株式会社アドバンテスト社外取締役 監査等委員(現任)
多様性を重視しながら進化を続ける取締役会
林: 当社のコーポレート・ガバナンス改革を振り返りますと、2021年3月期に社外取締役が取締役会議長に就任して以降、翌期には監査等委員会設置会社への移行や指名・報酬委員会の設置、中田取締役が当社初の女性取締役に就任するなど、年々ガバナンス機能を着実に進化させてきました。ガバナンス改革にはさまざまなアプローチがありますが、中でも社外取締役の強化は、経営の健全性・透明性確保に寄与する重要な要素の一つであると考えます。当社は2016年3月期より社外取締役制度を導入していますが、事業環境の変化が著しい昨今においては、取締役の多様性を確保し、多角的な知見を取り入れた上で、迅速かつ正確な経営判断を行うことの重要性は一層高まっていると感じます。
中田: 私が取締役に就任した当初は、社外取締役の発言はあったものの、活発な議論とまでは言えなかったと思います。その後、多様な人材を活用するダイバーシティ推進に関わってこられた松下取締役、メーカーで監査役を務められていた内藤取締役、商品開発の第一線で活躍されていた和田取締役が就任され、それぞれの専門性を活かして積極的に発言されており、今では社外取締役の発言の頻度は飛躍的に高まりました。弁護士の林取締役は、法的観点から、ここぞという大事なときに周りに流されずに厳しい意見を述べられます。私も弁護士ですが他社の社外取締役でもあり、法律のみならず株主や投資家目線での提言を行っています。さまざまな観点からより深く慎重な議論を実現するために、取締役の多様性の確保は有用と考えます。
内藤: 取締役会の多様性を活かしていくためには、出席者全員が闊達な議論に参加できる環境が必要であり、それが当社には備わっています。通常、常勤の取締役と社外取締役の情報差は広がりやすいものですが、社外取締役の出席しない経営会議・本部長会等の資料や議事録、業務監査部による内部監査記録等は閲覧権限の設定された社内ネットワークに随時格納されており、社外からも確認可能なため、当社の動きを理解する上で役立っています。それに加えて、監査等委員会に関しては、社内の各会議体で議論が交わされた重要な内容等を、常勤の有賀取締役が丁寧に説明してくれるので、より情報の解像度は高くなっています。
また、慎重な議論を要すべき案件については、取締役会に議題として挙げられる初回は概要説明と取締役による意見交換が行われ、より精査された内容を次回の取締役会にて審議するというプロセスがとられています。非常に複雑な案件があったとして、その場で理解し、その場で審議をするようでは、議論がし尽くされたと言うことはできません。質の高い議論を行うことは、リスクマネジメントの観点からも重要なことであり、このプロセスを大切にしていることは評価できます。
中田: 私たちの意見が尊重される風土も、取締役会の健全性・透明性確保の象徴と言えるのではないでしょうか。意見が実情に即していなければ保田社長を筆頭に常勤取締役の方々から丁寧に説明いただけますし、意見が的を射ていればすぐに採用されます。最近の例を挙げますと、2025年3月期の有価証券報告書は株主総会開催日の2日前に開示を行いましたが、本件については、2024年に当時の政府が有価証券報告書の早期開示に言及したときから「当社も準備すべきである」と申し上げていたもので、2025年3月の加藤大臣からの要請後すぐにその実施を提言したところ、保田社長が直ちに決断されて早期開示が実現しました。
ガバナンス強化につながった各々の取り組み
林: 2025年3月期で私が強く印象に残っていることはコンプライアンス関連への取り組みです。私は、これまでさまざまな団体でコンプライアンスアドバイザーとして携わってきましたが、この領域においては「今は良い状況にある」と油断をしていると問題が発生したり、詳しく調査をすると小さな火種が残っていたりするものです。社外取締役に就任して以降、当社では大きな問題があると認識したことはありませんが、火種がくすぶっている可能性は常に意識していて、継続的に微に入り細を穿つ必要があるものと考えています。
監査等委員会では「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、毎期末にガバナンス評価を行っています。2025年3月期の草案では全項目問題なしという評価となっていましたが、当期には軽微ながらコンプライアンス問題の火種になりかねない事案が散見されたことを踏まえ、開示を要するレベルではないものの、私は評価を「要改善」へと修正しました。また、違反者に対する懲戒の社内公示についても、従来の方法では類似事案への抑止力が十分とは言えず、改善策の提言を行いました。
内藤: 「内部統制システム構築の基本方針」は監査等委員会の役割として、業務監査部と連携した子会社の監査についても定めています。そこで、私はこれまで務めてきたメーカーの監査役(監査等委員)という視点から子会社の監査内容を見直し、労働安全衛生や設備保全に関する内容を拡充することを提言しました。生産保全に関連する部分は我々メーカーにとっての生命線であり、子会社であっても厳しく目を光らせなければなりません。もう一つの生命線として品質管理も挙げられますが、こちらについては、取締役会で品質に関する報告が毎月行われており、適宜取締役の意見を執行部門へとフィードバックすることで、適切な品質マネジメントを実施できています。品質課題に関しては、メーカー出身者である私に限らず、中田取締役の発言が後の品質改善に寄与したこともありました。
中田: ある品質課題について議論をしていた際に、当グループの品質マネジメントにおいて、社員の品質意識や報告ラインに改善の余地があるのではないかと言及した件ですね。後に、グループ全体に向けた動画による品質啓蒙活動が展開されることとなり、制作にあたって担当部門から意見を求められました。私は、知識の勉強というよりは身近なヒヤリ・ハット事例を入れた方が効果的と考え、社員の心に届く動画となるよう赤ペンで修正しコメントを述べ、その一部が動画にも反映されました。取締役がすべき作業ではないかもしれませんが、品質に限らず、大きな問題が現場で発生した際、それが然るべきルートで経営層へ伝達される環境を整備することも立派なガバナンスの一つです。社外取締役が積極的に関与したことでその重要性を再認識いただけたのではないかと考えています。
今後の意気込み
内藤: 品質啓蒙活動の件のみならず、2025年3月期に実施した「内部統制システム構築の基本方針」の全面見直しについても、主管部門と監査等委員会が積極的に意見を交わし、実効性の高い改訂を実現することができました。改訂後の方針は、監査等委員会の監査・監督機能をより明確にするとともに、迅速かつ効率的な経営判断・職務執行を可能とする内容となっています。今後、監査等委員会としては、当方針に則って委員各人が持つ専門的な知見を活かした取り組みを行い、執行部門と共にガバナンス体制の効果的な運用を図っていきます。
中田: 当社は、「こんなに良い会社があったんだ」と思うくらいの、知られざる優良企業です。社員の皆さんはどの方も驚くほど優秀で、福利厚生も充実しており、活き活きと仕事をしています。真面目な会社であり、グローバルに事業を展開しながらも、日本的な義理人情を大切にする温かい会社でもあります。私たち社外取締役に対する情報提供にも協力的で、社外取締役がより意見を言いやすい環境となるよう体制を進化させています。このような素晴らしい会社が持続的に成長し、中長期的に企業価値を向上していけるよう、今後も社外取締役としての客観的な視点から、取締役会や経営トップに率直に意見を述べ、また的確な監査・監督を行うことにより、さらなる経営の健全性と透明性の確保に努めていきます。
林: 社外取締役が把握する情報の拡充については、毎年行われている取締役会の実効性評価においても課題として挙げられていた件です。その差分を埋めてきたことで、来年控える第16次中期経営計画(2027年3月期~2029年3月期)の策定に際しても、取締役の多様性が反映された内容で形になり始めています。
それに連動して、私が議長を務める指名・報酬委員会においても、取締役や執行役員がより長期的な視点で、成果を意識して経営に臨むための報酬体系確立に向けて議論を行っています。社会情勢の変化やステークホルダーの期待を踏まえ、勉強会や意見交換を交えながら、より適切な制度設計を継続的に模索していきます。今後も、指名・報酬委員会を通じた役員報酬の見直しや経営体制の審議等を通じて、ガバナンスのさらなる向上と新たな価値創造に挑戦し続ける「喜ばれる企業」を目指していきます。

